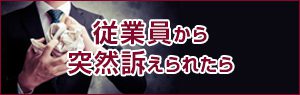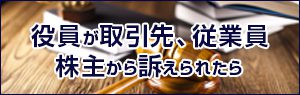「吸収合併」は「合併」の種類のうちの1つで、一方の法人格のみを残して他方の法人格を消滅させ、消滅する会社の権利・義務すべてを存続会社に承継させることです。
もう1つの合併である新設合併と異なり、実務において多く選ばれている手法といえます。
そこで、吸収合併とはどのような手法なのか、会社同士が1つになるメリット・デメリットについて解説していきます。
吸収合併とは
まず「合併」とは、複数の会社が合わさり1つの会社組織となる手法のことです。
合併には吸収合併と新設合併がありますが、吸収合併では一方の会社の法人格を残して、他方の会社の法人格を消滅させて消滅会社の権利・義務すべてを存続会社に承継させます。
消滅会社と存続会社の株主が1つの会社の共同株主になりますが、最終的に存続会社しか残らないのが吸収合併といえます。
吸収合併のメリット
吸収合併のメリットは、合併の効力発生後、すぐに1つの法人格で事業継続されることです。
株式譲渡よりも様々な統合効果を早く実現させることが期待できますが、さらに次のようなメリットがあります。
・対等な立場でM&Aが実現できる
・権利義務を存続会社に包括承継できる
・資金調達せず買収できる
それぞれ説明していきます。
対等な立場でM&Aが実現できる
吸収合併では、存続会社と消滅会社の合併比率が1:1の対等合併とすることで、対等な立場でM&Aを社内外に印象付けることができます。
権利義務を存続会社に包括承継できる
吸収合併により、権利・義務を包括承継できるため、承継すべき権利・義務が多いときにはメリットが大きいといえるでしょう。
資金調達せず買収できる
吸収合併で存続会社は、消滅会社の株主に合併対価を支払うことが必要ですが、現金以外に存続会社の株式・社債・新株予約権などを使うことができます。
吸収合併のデメリット
吸収合併の組織統合に関するデメリットは以下のとおりです。
・現場の負担が重い
・手続が煩雑
・取引縮小リスクがある
・買い手の持株比率が低下する
それぞれ説明していきます。
現場の負担が重い
吸収合併は合併の効力発生日から1つ会社として事業運営されるため、当日までに統合作業をある程度完了させておくことが求められるため、現場の負担は重くなりがちです。
手続が煩雑
吸収合併は組織法上の行為であるため、必要な手続を怠ったときには無効とされてしまいます。
株式譲渡より法的に求められる手続の数は多く、煩雑であることは留意しておきましょう。
取引縮小リスクがある
消滅会社と存続会社の共通の顧客がいた場合には、合併により存続会社のみとの取引となるため、取引を縮小されるリスクがあるといえます。
買い手の持株比率が低下する
合併による対価の支払いを株式とした場合、存続会社の株主は自身の持株比率が低下することになります。