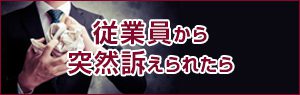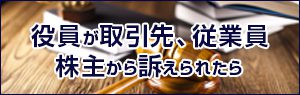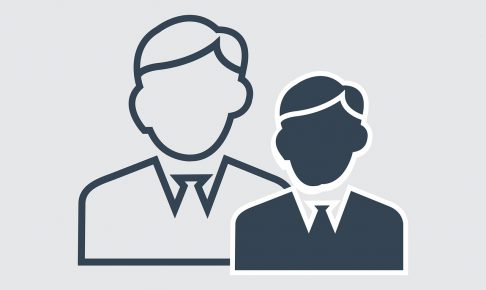会社は、職場のハラスメントについて被害者の従業員に対して損害賠償責任を負います。
しかし、会社だけでなく、取締役自身も責任を問われることがあります。
ただし、取締役がハラスメントの行為者かどうかによって、その責任の内容は変わります。
パワハラとは
「パワハラ」とは、「パワーハラスメント」のことであり、職務において高い地位や立場の方が優位性を利用し、適正な業務範囲を超えた精神的・身体的苦痛を与えることです。
会社役員のパワハラは、個人で民事責任(不法行為責任)と刑事責任(暴行罪・傷害罪など)を負わなければならない恐れがあります。
また、会社法429条1項により、役員の職務怠慢による損害発生の責任も負わなければならない恐れも否定できません。
役員個人だけでなく、会社も使用者責任に基づいた損害賠償責任を負う場合もあるため注意が必要です。
会社役員がハラスメント実行者である場合の責任
会社役員のハラスメント行為は、加害者である本人が以下の刑事責任と民事責任を負わなければなりません。
刑事責任
パワハラによる加害者になった場合、以下の刑事責任の対象になる恐れがあります。
・暴行罪
・傷害
・脅迫
・名誉毀損
・侮辱罪
上記の罪に該当し、懲役刑・禁固刑・罰金刑などを科される恐れがあります。
なお、セクハラの場合は、強制わいせつ罪または強制性交罪などの罪に該当する可能性があるといえるでしょう。
民事責任
民事責任は、被害者の損害を金銭で償わなければならない責任です。
ハラスメント行為で役員個人が刑事上の罪に該当する場合、その行為が不法な行為であることが明確になります。
それにより、役員は民法709条による被害者への損害賠償責任を負います。
使用者責任の要件
民法715条1項では、事業のために他人を使用する者は、被用者が事業執行について第三者へ加えた損害を賠償する責任を負うことが定められています。
そのため、使用者責任とは、従業員が職務上のミスなどで第三者に損害を与えた場合、その使用者である会社も損害賠償責任を負わなければならないことといえます。
使用者責任は、以下がなければ成立しません。
①従業員の不法行為で第三者に損害を与えた
②上記の不法行為は事業執行において発生した
③使用者と加害者である従業員が事実上の指揮監督関係にある
なお、③に関しては、使用者の事業実態や規模などで従業員の職務行為の範囲内に属すると認められれば、要件を充たすことになります。