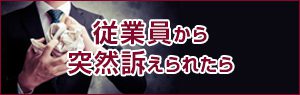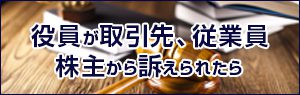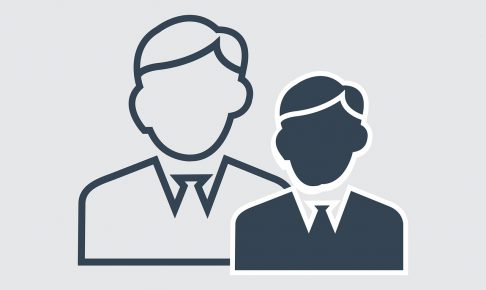管理監督者とは、経営者と一体的な立場であり、労働条件の決定や労務管理に関する権限を持つ労働者です。
役職名ではなく、労務管理を適切に行う上で欠かせない存在であり、職務内容・責任・権限・勤務様態によって該当するか判断されます。
そのため管理職だから管理監督者であるとは限りません。
そこで、管理監督者について、管理職との違いや認められる要件をわかりやすく解説します。
管理監督者とは
管理監督者とは、事業を拡大したり利益を増やしたりすることの実現に向けて、従業員の労働条件や労務管理を行う者であり、経営者と同じ地位や権限を付与された従業員です。
労働基準法第41条2号における、監督もしくは管理の地位にある者とされているため、法律上は特別な扱いを受けるため、時間外労働や休日出勤の割増賃金はありません。
また、労働時間の制限もないことが特徴です。
なお、労働基準法に管理監督者の配置義務の条文はないため、配置しなくても問題はありません。
管理監督者と管理職との違い
管理監督者と管理職を混同しがちであるものの、管理職の従業員の一部が管理監督者です。
そのため、管理職だから管理監督者であるとは限らず、必ずしも一致するわけではありません。
まず管理職は、法律上、厳密な定義はありません。
会社によって、たとえば課長以上または部長以上の役職を管理職とするなど異なります。
対する管理監督者は、労働基準法上で明確に定義があるため、課長や部長などの役職名にかかわらず勤務実態で判断することが必要です。
管理監督者の要件
管理監督者として認められるかは、会社内の職位や役職名ではなく、厚生労働省の通達などを参考に、以下の観点による実態が経営者と一体的な立場かにより判断します。
・職務…労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
・責任と権限…労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
・勤務態様…現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
・待遇…賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
管理監督者は、経営者とほぼ同じ立場で経営に関わる者であり、労働条件の取り決めや労務管理を経営者と一体的な立場で行います。
また、労働時間の規制の枠を超え、活動しなければならない重要な職務を有することも管理監督者の要件といえるでしょう。